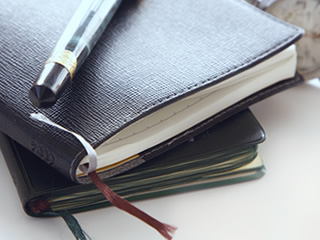<医療・介護・年金> ●6割以上の介護事業所が人手不足、離職率は 13 % 介護労働安定センターは7月 10 日、令和5年度介護労働実態調査結果を公表しました。従業員の過不足感は 64.7 %の事業所が「不足」と回答し、前年度に引き続き6割を上回りました。特に訪問介護員の不足感(81.4 %)が深刻となっています。事業所の平均採用率は 16.9 %、離職率は 13.1 %で、採用率が10 %未満の事業所が 43.3 %を占める一方、離職率が 10 %未満の事業所も約半数(50.7 %)を占めました。調査は令和5年 10 月に9,077 事業所の回答を集計しました。 ●令和6年 10 月から先発医薬品の選定に特別料金 令和6年度の診療報酬改定により、後発医薬品ではなく先発医薬品の処方を希望(選定療養)する患者に1~3割の自己負担に加えて特別料金の支払いを求める仕組みが導入され、令和6年 10 月から適用されます。特別料金は先発医薬品と後発医薬品の薬価差の4分の1に相当する額で、厚生労働省は7月 12 日、その計算方法や解釈などを事務連絡しました。先発医薬品を処方する医療上の必要があると認められる場合には対象外となりますが、薬剤の使用感や味など、それ以外の理由は特別料金を求め、安価な後発医薬品の使用を促します。 ●企業年金等のアセットオーナーに共通原則 政府は8月 28 日、アセットオーナー・プリンシプルを策定しました。公的年金、企業年金などのアセットオーナー(機関投資家)に求められる共通の原則を定めるもので、法的拘束力はありませんが、受益者等の最善の利益を追求するため運用方針の策定や適切なリスク管理、運用状況の見える化など5つの原則に基づく取り組みを促します。受け入れるアセットオーナーはその旨を表明し、政府はそのリストを公表する方針です。なお、受け入れを表明した場合でも、すべての原則に対応する必要はなく、実施しない原則はその理由を説明します。 <統計・その他> ●フリーランスで働く人のトラブル、報酬関係多く 連合は8月5日、フリーランスとして働く人の意識・実態調査 2024 の結果を公表しました。それによると、フリーランスとして仕事上でトラブルの経験があると回答した者は 46.6 %に及び、その内容は、不当に低い報酬額の決定(28.8 %)、報酬の支払いの遅延(25.8 %)、報酬の不払い・過少払い(24.9 %)など、報酬関係が多いことがわかりました。令和6年 11 月に施行される特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律は、これらをいずれも禁止行為としています。調査は、全国の 20 歳以上の男女でフリーランスとして働く人 1,000 名を対象に令和6年6月に実施しました。 ●「こころの健康」に着目ー令和6年版厚生労働白書 厚生労働省は8月 27 日、令和6年版厚生労働白書を公表しました。白書として初めて「こころの健康」に着目し、健やかに暮らすことができる社会づくりの方向性を考察しました。白書によると、精神疾患を有する外来患者が令和2年に約 586 万人に達し、身体の健康よりこころの健康に対するリスクを重視する人(15.6 %)も 20 年間で約3倍に増えています。白書は地域や職場におけるこころの健康づくりの取り組みを紹介し、その共通の理念として「当事者の意思の尊重と参加」を指摘しました。 ●有効な子育て支援「両立できる職場環境」約4割 厚生労働省が8月 27 日に公表した令和4年社会保障に関する意識調査によると、有効だと考える子ども・子育て支援対策で回答が最も多かったのは、子育てと仕事が両立できる職場環境の推進で約4割(40.9 %)を占めました。働きながら子育てするための制度の充実(37.6 %)も多く、子ども・子育て支援には職場の環境や制度が大きな影響を及ぼすことが改めて確認されました。調査は令和4年7月に 20 歳以上の男女 7,128 人の回答を集計しました。 |