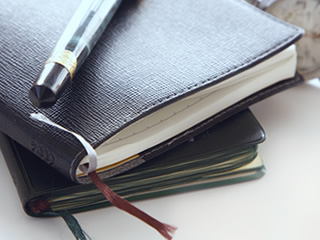<医療・介護・年金> ●協会けんぽが令和6年度健康保険料率を改定 協会けんぽは1月 29 日、令和6年度の都道府県別の健康保険料率を決定しました。最高料率となるのは佐賀支部の 10.42 %で 14 年連続となります。最低料率は新潟支部の 9.35 %となり、10 年連続でした。全国平均保険料率はこれまでの 10.0 %を維持。前年度より料率を引き上げるのは 24 支部。引き下げるのは 22 支部。据え置きは1支部(神奈川支部)でした。なお、令和6年度の介護保険料率は 1.60 %となります。 ●医療・介護・保育分野の職業紹介事業を集中指導へ 厚生労働省は2月9日、医療・介護・保育分野の職業紹介事業の状況について社会保障審議会医療部会に説明しました。深刻な人手不足を背景に民間の職業紹介事業の役割が高まるなか、高額な紹介手数料を支払っても早期離職してしまう事例があり、部会では悪質な事業者への対応を求める意見が相次ぎました。同省では、すでに手数料等の情報開示義務や、就職後2年間の転職勧奨の禁止などの対策を講じていますが、今後も3分野の有料職業紹介事業者に対する集中的指導監督などを実施します。あわせて3分野におけるハローワークの機能強化も図る方です。 ●被用者保険のさらなる適用拡大に向けて懇談会開く 厚生労働省は2月 13 日、働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会の初会合を開きました。さらなる適用拡大に向けて、ヒアリングなどを実施しながら今後の対応を検討し、今夏までに社保審年金部会に報告します。主な検討事項は、短時間労働者及び個人事業所に対する適用拡大と、複数の事業所で勤務する者やフリーランスなどの多様な働き方を踏まえた被用者保険のあり方などです。この日の意見交換では、適用拡大を進める方針は一致しましたが、保険料負担が生じる企業や財政影響が懸念される医療保険者への配慮を求める意見も出されました。 ●令和6年度診療報酬改定答申、賃上げ対応に重点 中医協は2月 14 日、令和6年度診療報酬改定について答申しました。例年4月に改訂されますが、DX推進に向けて医療機関等やベンダの負担を平準化するため令和6年6月に実施されます。重要課題の1つとされる医療従事者の賃上げ対応では、初診料・再診料や入院基本料等を引き上げるほか、ベースアップ評価料を新設します。同評価料は、医師以外の看護職員やリハビリ職員などの職種を対象として、令和6年度及び7年度に定期昇給以外の賃上げを行うことなどが要件で、算定する医療機関は賃上げの計画書と報告書を地方厚生局等に提出することが求められます。 ●存続厚生年金基金の対応方針、3月末までに結論 厚生労働省の社保審企業年金・個人年金部会は1月 29 日、存続する厚生年金基金の今後の対応に関して検討を開始しました。3月末までに結論を出す予定です。いわゆる「代行割れ問題」の発生から厚生年金基金の自主的な解散を促した健全化法の附則2条は、施行から 10 年後の 2024 年3月末までに存続厚生年金基金の解散または他の企業年金制度への移行を促し、必要な法制上の措置を講じるよう求めています。現存する5基金はいずれも財政状況が良好で、4基金が存続の意向を示していますが、2月 27 日に開催した部会では、すでに廃止された制度が存続する行政コスト、将来的な厚生年金財政への影響懸念、すでに解散・代行返上した他基金との公平性などの観点から、解散または代行返上に向けた道筋を示すべきとする意見が多くを占めました。しかし、基金は退職給付などの労働条件との関連性が強く、解散等は当該基金の労使判断を尊重すべきとする意見も根強いです。 <統計・その他> ●技能実習制度廃止後の新制度で政府方針を決定 政府は2月9日、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議を開催し、技能実習制度及び特定技能制度のあり方に関する政府の対応方針を決定しました。今国会に改正法案を提出する予定です。技能実習の廃止後は、人材確保と人材育成を目的とする制度(育成就労制度)を創設します。その受け入れ分野は現行の特定技能の特定産業分野を基本とし、技能実習対象職種の実態を踏まえ産業分野の拡大を検討します。新制度では、技能実習では認められなかった本人の意向による転籍も容認しますが、その要件の1つとされる日本語能力は、新たな水準の試験を創設する考えです。同じく転籍の要件とされる就労期間は、当初の受け入れ機関で1年以上就労することを基本としながらも、当分の間は、各分野の実情を踏まえ、分野ごとに1年~2年の範囲内で設定することを認めています。 ●賃上げする中小企業の約6割が業績改善なく実施へ 日本商工会議所は2月 14 日、中小企業の人手不足、賃金等に関する調査結果を公表しました。それによると、令和6年度に賃上げを実施する予定の中小企業は、61.3 %と6割を超え、昨年度(58.2 %)から 3.1 ポイント増加しました。このうち約6割(全体の 24.4 %)の中小企業は、業績の改善が見られない中でも賃上げを実施する予定であることがわかりました。こうした賃上げを行う理由としては「人材の確保・採用」が8割近く(76.7 %)に及び、「物価上昇への対応」が約6割(61.0 %)で続いた。調査は令和6年1月に実施し、中小企業 2.988 社の回答を得ました。x ●令和5年出生数は 75.8 万人で過去最少ー厚生省速報 厚生労働省が2月 27 日に公表した人口動態統計速報によると、令和5年の出生数は前年(79 万 9,728 人)から4万 1,097 人減少して、75 万 8,631 人となることがわかりました。8年連続の減少で、過去最少を更新しました。一方、死亡数は 159 万 503 人で過去最多を更新し、差し引きの自然増減数は 83 万 1,872 人で過去最大の減少幅となりました。婚姻件数も前年から3万 542 組減少して 48 万 9,281 組となり、今後も少子化傾向が続く懸念が深まります。政府は、若年人口が急減する 2030 年代に入るまで少子化傾向を反転させる重要な分岐点だとしていて、こども未来戦略に基づく少子化対策の着実な実行をめざします。 |