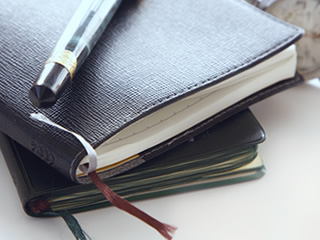<医療・介護・年金> ●令和6年度診療報酬は 0.88 %のプラス改定 厚生労働省は昨年 12 月 20 日、医療や介護、障害サービス等の公定価格となる令和6年度の診療報酬・薬科等改定と介護報酬、障害福祉サービス等報酬改定の改定率を決定しました。診療報酬は+ 0.88 %、薬価等は▲ 1.00 %、介護報酬は+ 1.59 %、障害福祉サービス等は+ 1.12 %とします。診療報酬に関しては、診療所の好調な経営状況等から財務省が大幅なマイナス改定を主張していましたが、物価高騰への対応や勤務医、看護職員等の賃上げ分を確保しています。介護報酬や障害サービス等も職員の処遇改善分が多くを占めています。 ●介護保険の2割負担の判断基準は引き続き検討 厚生労働省は昨年 12 月 20 日、年末の予算編成過程で検討するとしていた介護保険の利用者負担2割の対象となる「一定以上所得」の判断基準見直しについて、令和6年度からの実施を見送り、令和9年度までに検討して結論を得る方針を決定しました。22 日に開催した社会保障審議会介護保険部会に報告しました。検討にあたっては、一定の負担上限額を設けずとも負担増に対応できると考えられる所得を有する利用者に限って2割負担の対象とするとともに、当分の間、一定の負担上限額を設けた上で、前述よりも広い範囲の利用者を2割負担とする案を軸とします。利用者負担に対する金融資産の保有状況等の反映や、きめ細かい負担割合のあり方もあわせて検討する方針です。 ●こども・子育て支援金制度は令和8年度から開始 政府の全世代型社会保障構築本部は昨年 12 月 22 日、こども未来戦略と全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)を決定しました。こども未来戦略では、少子化対策の加速化プランの予算規模として 3.6 兆円程度の充実を見込み、その安定財源確保に向けて「こども・子育て支援金制度」を令和8年度から 10 年度にかけて段階的に構築することを決定しました。改革工程によって示された医療・介護制度等の歳出改革を賃上げによって社会保険料負担軽減効果を生じさせ、その範囲内で支援金制度を支援金制度を構築するとしました。なお、改革工程では、歳出改革として医療・介護の利用者負担割合の見直しなどが提言されています。 ●健康保険証の廃止は令和6年 12 月2日に決定 武見厚生労働省大臣は昨年 12 月 22 日、現行の健康保険証の新規発行を令6年 12 月2日で終了すると公表しました。この日、マイナンバー法等の一部改正法の施行期日を同日と定める政令が閣議決定されました。マイナンバーの紐づけ誤りの事案の総点検は令和5年内で終了し、不一致データの確認作業も今春までに完了する見通しであることから、政府のマイナンバー情報総点検本部において、健康保険証の発行を予定どおりに終了し、マイナ保険証を基本とするしくみに移行する方針が確認されていました。健康保険証の廃止後も最大1年間は現行の保険証を使用可能とし、マイナ保険証を保有しない人には申請によらず資格確認書を発行します。12 月1日に保険証の年次更新を行う保険者の被保険者が十分な経過措置を受けられるようにする理由などから、翌2日の施行となります。 ●令和6年度年金額改定は+2.9%の見込み 政府は昨年 12 月 22 日、令和6年度予算案を閣議決定しました。年金の一般会計予算案は、基礎年金国庫負担分などで 13 兆 3,237 億円を計上しています。令和6年度の年金額改定は+ 2.9 %と見込み、年金スライド分として 3,518 億円を確保しました。改定率の指標となる物価変動率は+ 3.4 %、名目手取り賃金変動率は+ 3.3 %、マクロ経済スライド調整率は▲ 0.4 %となり、令和6年度は物価変動率が賃金変動率を上回るため、新規・既裁定者ともに賃金変動率をもとに改定される見通しです。なお、あくまで予算上の見込みであり、実際の改定率は令和5年度の消費者物価指数が公表される1月中旬に確定します。 <統計・その他>●勤務時間外の業務上の連絡、6割が「ストレス」 連合が昨年 12 月7日に公表した「つながらない権利」に関する調査 2023 の結果によると、雇用者の7割以上(72.4 %)が「勤務時間外に部下・同僚・上司から業務上の連絡がくることがある」と回答したことがわかりました。「勤務時間外に取引先から業務上の連絡がくることがある」と回答した者も4割以上(44.2 %)に及びました。勤務時間外の業務上の連絡に関して「ストレスを感じる」回答した雇用者は、部下・同僚・上司からの連絡は 66.2 %、取引先からの連絡は 60.9 %で、いずれも6割以上を占めています。調査は 2023 年9月に 18 歳~ 59 歳の雇用者等 1,000人を対象に実施し、雇用者 942 人の回答を得ました。 ●官報発行の法律公布、令和7年春までに電子化 官報の電子化に向けて「官報の発行に関する法律」及び関連法が昨年 12 月6日に成立し、13 日に公布されました。令和7年春までに施行される予定です。明治 16 年の官報創刊以来、慣行として行われてきた官報の発行について、国の法令や公示事項を掲載して国民に周知するための「国の公報」と法律で位置づけるとともに、原則として紙の印刷物による発行をやめるウェブサイト上で公開されます。法令等の公布は、官報をもって行うことも規定しています。ウェブサイトでの公開は、内閣府令で定める期間とされますが、法令や政府調達公告等の情報は永続的に公開されます。他方、インターネットを利用できない人への配慮として官報の情報を配慮した書面を販売書面を販売するなどの措置も講じます。 |