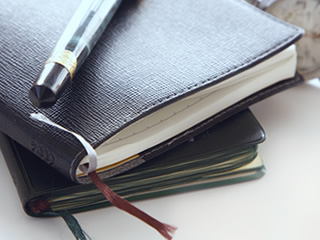厚生労働省の社保審介護給付費分科会は1月 22 日、令和6年度の介護報酬改定案を了承し、答申しました。介護職員の処遇改善に関しては、現行の加算を組み合わせて一本化されます。基本報酬に関しては、実態調査で赤字となった介護老人福祉施設や介護老人保健施設の報酬を引き上げる一方、収支差率が高い訪問介護を引き下げます。また、令和6年度から義務化される業務継続計画(BCP)を未策定の事業所に対する報酬減算を盛り込みました。施行は例年どおり令和6年4月を基本としますが、医療の診療報酬改定が令和6年6月に施行されることから、訪問看護やリハなど医療系サービスなどは6月の施行となります。
●「ビジネスと人権」に取り組む企業が76%に
経団連は1月 16 日、企業行動憲章に関するアンケート調査結果を公表しました。調査は前回(2020 年)から3年ぶりに実施されたもので 286 社の回答を集計しています。それによると「ビジネスと人権」に関して、国連の指導原則に基づき取り組みを進めている企業は 76 %となり、前回(36 %)から2倍以上に増加しました。具体的には「人権方針の策定」が 91 %、自社の従業員に対する「研修会」実施が 79 %、子会社・グループ会社を対象としたものも 66 %に及びました。取引先への働きかけでは、人権尊重の考え方等を調達方針で明確化した企業が 94 %に達した一方、「サプライズチェーンの構造が複雑・膨大であり、課題の特定が難しい」(73 %)、「一社・企業だけでは解決できない複雑な問題がある」(72 %)などの課題も指摘されました。
●フリーランスの業務委託「1ヵ月」以上で規制強化へ
公正取引委員会は1月 19 日、特定委託事業者に係る取引の適正化に関する検討会の報告書を公表しました。報告書を踏まえ公取委は、政省令及び指針等の制定作業に着手します。今秋までに施行されるフリーランス法は、事業者がフリーランスに政令で定める期間以上の業務委託をする際、受領拒否や報酬減額、返品などの行為を禁じます。報告書はこの禁止行為の対象となる業務委託期間を「1ヵ月以上」と提言しています。他方、省令に委任される業務委託の際に事業者が行う明示義務は、明示事項とする項目の方向性を示しました。このうち知的財産権の帰属に関しては、明示義務までは求めないものの、作成目的である使用の範囲を超えて事業者が知的財産権を自らに譲渡・許諾させることを含んで発注する場合、その範囲を明確に記載するよう求める考えです。