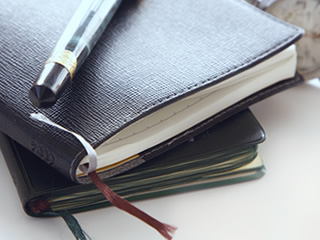<労働基準> ●令和6年度地域別最低賃金改定へ審議開始<div> 厚生労働省の中央最低賃金審議会は6月 25 日、令和6年度地域別最低賃金改定に向けて審議を開始しました。7月末を目途に改定の目安を示す方針です。令和5年度は全国加重平均が前年度から 43 円増の 1,004 円、引き上げ率は 4.47 %となりいずれも過去最高を更新しました。武見敬三厚生労働大臣は、春闘の5%を超える賃上げの流れを非正規雇用や中小企業に波及させるため最低賃金の引上げが必要であると強調するとともに、政府として中小企業の価格転嫁や生産性向上などを後押しすると表明しました。また、物価上昇にも配慮した審議を求めました。 ●パート等の賃金決定考慮要素、最低賃金が過半数 厚生労働省は6月 25 日、中賃審の目安に関する小委員会を開き、労働政策研究・研修機構が実施した令和5年の最低賃金引上げに関する調査の速報値を報告しました。それによると、パート・アルバイトの賃金を決定した際の考慮要素として過半数の(51.1 %)企業が地域別最低賃金と回答しました。職務(35.3 %)、経験年数(32.8 %)、地域の賃金相場(25.8 %)を上回りました。調査は、従業員 300 人未満規模の 8,206 社の回答を集計しました。 ●過労死等の請求 4,500 件超で過去最多を更新 厚生労働省が6月 28 日に公表した令和5年度の過労死等の労災補償状況によると、過労死等の請求件数は前年度から 1,112 件増加して 4,598 件、支給決定件数は同 193 件増の 1,097 件となり、いずれも過去最多を更新しました。過労死等のうち脳・心臓疾患の請求件数は 1,023 件で過去最多です。同じく精神障害の請求件数も 3,575 件で最多でした。過労死等が急増する背景について同省は、脳・心臓疾患のリスクが高い高年齢労働者の増加や、精神障害の労災請求に対する社会的な認知が広がったことなどが要因ではないかと分析しています。 <雇用> ●教育訓練後5%の賃上げを要件に追加給付 厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会は6月 21 日、教育訓練後5%以上の賃上げがあった場合に追加給付(10 %)を行う専門実践教育訓練給付金の改正などを定めた雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を妥当と認めました。令和6年 10 月1日から施行されます。要件とされる賃上げは、訓練前後の6ヵ月間の賃金日額を算出し、訓練後の賃金が訓練前の賃金の 105 %相当額以上であれば要件を満たします。対象が離職者の場合は、訓練開始日前の直近の離職に係る賃金日額と、資格取得等をして雇用された後1年間における任意の6ヵ月間の賃金を比較します。在職者の場合は、訓練開始日の前日を離職日とみなした賃金日額と、資格取得後1年間における任意の6ヵ月間の賃金を比較します。 ●改正育介法の施行は令和7年4月と 10 月に 厚生労働省は6月 26 日、令和6年通常国会で成立した改正育児・介護休業法の改正事項のうち、公布日(5月 31 日)から1年6ヵ月以内とされていた子が3歳以降の柔軟な働き方を実現するための措置の創設、妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前の個別の意向聴取・配慮の施行日について、令和7年 10 月1日とする方針を労政審雇用環境・均等分科会に提示しました。そして了承されました。また同省は、法律の附帯決議で要請された介護休業等の対象となる要介護状態の判断基準の見直しについて、こども家庭庁とともに検討会を発足して検討を進める考えを表明しました。このほかの改正事項と合わせて、令和7年4月1日そ施行を目指すとしました。 ●地域指数訂正に伴う派遣元の対応支援に助成金 厚生労働省は6月 28 日、令和6年度の一部賃金水準の地域指数の訂正に伴い、労使協定の再締結や派遣労働者への追加の賃金支払いなどの対応が必要となる派遣元事業主への支援措置として、雇用保険二事業の人材確保等支援助成金に令和6年度限りの暫定措置を設ける雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を公布・施行しました。協定の再締結等の整備に係る基本経費として5万円、追加的に賃金を支払う派遣労働者1人につき1万円を助成します。同省は、派遣元から提出される事業報告書をもとに対応が必要な派遣元をすべて把握できるため、都道府県労働局を通じて個別に対応を促すとともに、支援措置などを周知する考えです。 |