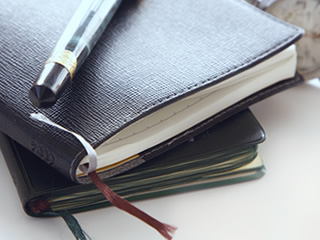<医療・年金> ●定年延長時における給付減額の判定基準見直しへ 厚生労働省は 11 月8日、定年延長の阻害要因と指摘されていた確定給付企業年金(DB)の給付減額の判定基準の見直しについて、社会保障審議会企業年金・個人年金部会に提案しました。現行制度では定年延長に伴い、給付額を維持する場合でも、定年年齢(支給開始年齢)までの期間が長くなることから、計算上は現在価値(通常予測給付現価や最低積立基準額)が減少し、給付減額に該当します。対象者の個別の同意等を得る必要がありました。見直し案では、給付の名目額が増加することなどを要件に、対象加入者の3分の2以上で組織する労働組合の合意があれば、例外的に給付減額として取り扱わないこととします。 ●糖尿病の障害等級認定に医師照会様式を活用へ 厚生労働省は 11 月8日、糖尿病に係る障害等級の認定の際に活用する医師照会様式を作成し、日本年金機構に事務連絡しました。障害年金に請求の際に必要と判断された場合は、自己対処等の必要も含めた日常生活の制限度合いや糖尿病の特性、血糖コントロールの状態、症状、労働の状況を含む具体的な日常生活状況等を医師が確認して記載します。認定の判断材料とします。糖尿病患者に対する障害基礎年金の支給停止処分が違法だとされた令和6年4月 19 日の大阪高裁判決を踏まえた措置です。 ●高額医療費制度見直しへ厚労省が審議開始 厚生労働省は 11 月 21 日、社会保障審議会医療保険部会を開き、高額医療費制度の見直しを提案しました。自己負担限度額を引き上げるとともに、所得区分を細分化します。現行は年収に応じて 70 歳未満が5区分、70 歳以上が6区分に分かれています。高齢化の進展や医療の高度化などで高額医療費の総額が増加していて、政府の全世代型社会保障構築会議も 2028 年度までの実施を求めていました。 <統計・その他> ●経済政策を決定、103 万円の壁引上げ明記 政府は 11 月 22 日、総合経済対策を閣議決定した。すべての世代の現在・将来の賃金・所得を増やすーーを柱の1つに捉え、2020 年代に全国平均 1,500 円を目標とする最低賃金に引き上げや、価格転嫁を促す下請法の執行強化及び法改正の検討などを施策に掲げました。また所得税の「103 万円の壁」については、令和7年度税制改正で議論し引上げるとしました。政府は、経済政策の裏づけとなる令和6年度補正予算の早期成立をめざします。 ●新生児に顔写真なしマイナカードの交付開始 政府は 12 月2日、申請日に1歳未満の者に対して、顔写真なしのマイナンバーカードを交付する運用を開始しました。申請から原則1週間で発行される特急発行の対象で、出生届と同時に申請できます。5歳の誕生日まで有効です。医療保険者の加入手続・登録後にマイナ保険証の利用登録が可能ですが、医療機関等でのオンライン資格確認は4桁に暗証番号入力が必要で、顔認証や目視による利用は不可です。マイナ保険証による受診を希望しない場合には、資格確認書の交付を受けることができます。 |