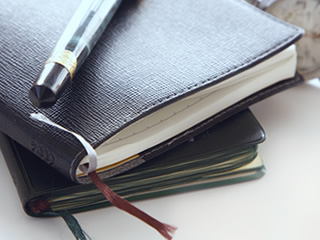厚生労働省は 11 月 15 日、労働者に営業ノルマ未達分や売れ残った商品の買取りを強要する、いわゆる自爆営業について、労働関係法令上の考え方を整理し、規制改革推進会議のWGに説明しました。自社商品の購入代金を労使協定なく賃金から控除する場合は、労働基準法第 24 条違反となり、またノルマ未達成時に労働者負担で商品を購入すると規定に定めた場合、それが労働契約の不履行についての違反金の定めと評価されれば、同法第 16 条違反になるとしました。また、使用者としての優越的な立場を利用して買取りを強要するなど、一定の要件を満たせばパワーハラスメントに該当する可能性を示唆しました。WGでは、自爆営業をパワハラの一類型として指針で明示できないか、同省の検討を求める意見が相次ぎました。
厚生労働省は 11 月 17 日、書面掲示などのアナログ規制をデジタルで完結する規制に見直す省令改正に着手しました。最低賃金法施行規則、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令、作業環境測定法施行規則の3省令を改正し、令和6年3月末から施行します。最賃則の改正では、都道府県労働局長が地域別最低賃金を決定する際に聴く地方最低賃金審議会の意見の要旨の公示について、労働局の掲示板に書面掲示を求める規則を労働局のウェブサイトに掲載すると改めます。安衛法の登録省令及び作環則の改正も同様に見直します。
<雇用>
●仕事と介護の両立支援でガイドライン策定へ
経済産業省は 11 月6日、企業経営と介護両立支援に関する検討会の初会合を開きました。仕事をしながら家族等の介護に従事する「ビジネスケアラー」が増加するなか、企業の両立支援の取り組みを促すガイドラインを年内に策定します。従業員の介護による企業経営上の影響、両立支援の効果、企業実態に応じた施策等の調査分析を踏まえ、政府の支援策のあり方も検討します。同省によると、ビジネスケアラーは 2025 年に 307 万人、2030 年には 318 万人になると見込まれ、労働生産性低下や介護離職等による経済損失額は約9兆円に及ぶと推計されています。
●両立支援等助成金に業務代替支援の新コース
厚生労働省の労働政策審議会雇用環境・均等分科会は 11 月 20 日、両立支援等助成金に育休中等業務代替支援コースを創設する雇用保険法施行規則の改正省令案を妥当としました。政府の経済対策に盛り込まれたもので、令和6年1月から施行されます。労働者が育児休業または育児短時間勤務制度を利用する期間に業務を代替する労働者に手当支給等をした事業主に最大 125 万円(育短勤務は最大 110 万円)を助成するほか、育休期間中に代替要員を雇用した事業主に最大 67.5 万円助成されます。このほか省令案には、産業雇用安定助成金やキャリアアップ助成金の拡充などを規定されています。いずれも 12 月上旬の公布日施行です。
●雇用保険の適用拡大を労政審が大筋了承
厚生労働省の労政審職業安定分科会雇用保険部会は 11 月 22 日、週 20 時間未満の労働者に対し、雇用保険の適用を拡大する方針を大筋で了承しました。2028 年度までの実施に向けて、今後は適用基準となる週所定労働時間どこまで引き下げるかが論点となります。同省によると、週 10 時間以上にまで拡大した場合は、最大約 500 万人、週 15 時間以上まで拡大した場合は最大約 300 万人が新規に適用される見通しです。申請手続等を含む事業主の負担増、給付と負担のバランス、制度運営コスト等を踏まえて検討し、令和6年の通常国会に雇用保険法の改正法案の提出をめざします。
●マルチ高年齢被保険者 219 人ー厚労省が状況報告
厚生労働省は 11 月 22 日、令和4年1月に施行された雇用保険のマルチジョブホルダー制度による被保険者(マルチ高年齢被保険者)の状況を労政審に報告しました。施行から令和5年9月までにマルチ高年齢被保険者になった者は 219 人で、性別は男性が4割(87 人)、女性が6割(132 人)を占めました。年齢は 65 歳が最も多く 45 人、平均年齢は 69 歳でした。週所定労働時間は平均 27 時間で、約7割を 30 時間未満が占めました。同制度は、複数の事業所(週所定 20 時間未満)で雇用される者の申出に応じて、2つの事業所の労働時間を合算して雇用保険に適用される制度です。65 歳以上の者を対象に、試行的に実施されています。