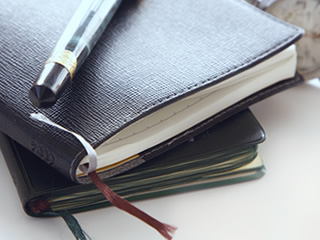財務省の財政制度等審議会は 11 月 20 日、令和6年度予算編成等の建議をまとめました。令和6年度診療報酬改定については「マイナス改定が適当」とし、財務省の調査で経営状況が良好とされた診療所の報酬単価引き下げなどを主張しました。具体的には、診療所の経常利益率 8.8 %が全産業やサービス産業平均(3.1~ 3.4 %)と同程度になるよう 5.5 %程度の引き下げを要求しました。これにより保険料負担は年間 2,400 億円程度の軽減が見込まれ、現役世代の保険料率も 0.1 %程度の軽減が見込まれるとしました。診療報酬の改定率は年末の大臣折衝で決定する予定です。
厚生労働省は 11 月 21 日、社会保障審議会年金部会を開き、マクロ経済スライドによる厚生年金(報酬比例部分)と基礎年金の調整機関のズレと、基礎年金の調整期間の長期化に伴う給付水準の大幅な低下への対策として、国民年金と厚生年金の財政を合体して調整終了年度を一致させる試算を説明しました。一致させた場合、 2033 年で調整が終了する見込みです。同省によると、調整期間の一致で報酬比例部分の所得代替率は 1.9 %低下しますが基礎年金は 6.4 %上昇し、基礎年金と報酬比例部分を合わせた全体は 55.6 %と 4.6 %の上昇が見込まれます。マクロ経済スライドは基礎年金及び報酬比例部分それぞれの財政が均衡するまで給付の伸びを抑制するしくみですが、デフレ下では発動せず、特に基礎年金の財政が悪化となります。報酬比例部分は 2025 年で調整が終了する一方、基礎年金は 2046 年まで調整が長期化する試算が示されていました。
<統計・その他>
●令和4年の年次有給休暇取得率 62.1 %で過去最高
厚生労働省は 10 月 31 日、令和5年就労条件総合調査結果を公表しました。それによると、令和4年の年次有給休暇の取得率は 62.1 %となり、前年を 3.8 ポイント上回って過去最高を更新しました。8年連続の上昇となっています。労働者1人あたりの平均取得日数は、10.9 日(前年 10.3 日)でした。政府は年次有給休暇の取得率を令和7年までに 70 %以上とする目標を掲げています。調査は、常用労働者 30 人以上の民営企業 6,421 社を対象に実施し、3,768 社から有効回答を得ました。
●「心の病」が最も多い年齢層に 10 ~ 20 歳代急増
日本生産性本部が 11 月9日に公表した 2023 年のメンタルヘルスの取り組みに関する企業アンケート調査結果によると、「心の病」が最も多い年齢層として 10 ~ 20 歳代が 2021 年の 29.0 %から 43.9 %と急増し、30 歳代(26.8 %)を初めて上回り、最も多い年齢層になりました。40 歳代は 21.3 %、50 歳代以上は 7.9 %となっています。コロナ禍で入社した若手層テレワーク等で対人関係や仕事のスキルを十分に積み上げられないなか、5類移行に伴う出社回帰の変化が大きなストレスになった可能性があります。調査は 2021 年に続き 11 回目となります。上場企業 169 社の人事担当者からの回答を集計しました。
●派遣料金引き上げの要望受けた事業所は約4割
厚生労働省は 11 月 24 日、令和4年派遣労働者実態調査結果を公表しました。調査は平成 29 年以来5年ぶりに実施したもので、派遣労働者の同一労働同一賃金施行後初めてです。その事業所調査によると、派遣労働者の不合理な待遇差解消のため、派遣元から派遣料金に関する要望があった事業所は約4割(38.0 %)に及び、そのうち求めに応じて派遣料金を上げたことがある事業所は9割以上(91.4 %)になることがわかりました。一方で、求められたものの派遣料金を維持した事業所は2割(20.3 %)でした(複数回答)。調査は5人以上の常用労働者を雇用する事業所約 17,000 ヵ所に実施し、有効回答率は 49.7%でした。
●人員確保や物価上昇を背景に賃上げ額が過去最高
厚生労働省が 11 月 28 日に公表した賃金引き上げ等の実態調査結果によると、令和5年に賃金を引き上げた・引き上げる企業は 89.1 %で前年(85.7 %)を上回るとともに、1人あたりの賃金改定額の平均も 9,437 円と、前年(5,534 円)を大きく上回ったことがわかりました。改定率は 3.2 %で額・率ともに比較可能な 1999 年以降、過去最高です。賃金改定にあたって企業が重視した要素は、企業の業績が 36.6 %(前年比 3.4 ポイント減)に低下する一方で、労働力の確保・定着が 16.1 %(同 4.2 ポイント増)、雇用の維持が 11.6 %(同 0.9 ポイント増)と上昇しています。また、物価の上昇を最も重視した企業も前年の 1.3 %から 7.9 %と急増しました。調査は常用労働者 100 人以上を雇用する企業を対象に実施し、1,901 社の回答を得ました。