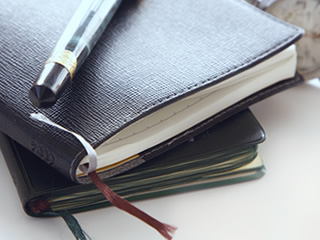こども家庭庁は3月 29 日、児童手当や育児休業給付の拡充など加速化プランの実施に充てる財源として、医療保険から徴収する子ども・子育て支援金について試算額を示しました。支援金制度は令和8年度から段階的に導入するとされていて、被用者保険の被保険者1人当たりに平均月額は、令和8年度が 450 円、令和9年度が 600 円、令和 10 年度は 800 円と試算しました。金額は事業主負担分を除いた本人拠出金であり、被用者保険においては事業主が労使折半の考えの下で拠出します。
●フリーランスに関するルール正解者は4割弱に
連合は3月7日、ワークルールに関する調査結果を公表しました。調査は 2024 年1月にフリーランスなどを含む労働者等 1,000 名の回答を集計しました。それによると「フリーランスも労働者なので労働時間や給料など最低限は法律で守られる:正解は✕」を正解した者は4割弱(37.9 %)にとどまり最も正解率が低いものとなりました。次いで低かったのは「会社指定の制服に、会社の更衣室で着替えている時間は労働時間に含まれない:正解は✕」で正解した者は7割弱(68.4 %)でした。他方、勤務時間外のイベントへの参加強要や、ハラスメントに関するルールなどは、正解者がいずれも8割を超えました。
●賃上げ率は5%超ー連合が春闘の回答集計を公表
連合は3月 15 日、2024 年春闘の第1回回答集計結果を公表しました。回答集中日(3月 13 日)の結果を含む 771 組合の賃上げ額(加重平均)は、昨年同時期から 4,625 年増の1万 6,469 円、賃上げ率は同 1.48 ポイント増の 5.28 %となり、1991 年以来 33 年ぶりに5%を超えたことがわかりました。22 日に公表された第2回回答集中においても、1,446 組合の賃上げ額は1万 6,379 円、賃上げ率は 5.25 %となり、引き続き5%を維持しています。
●不妊治療との両立支援制度等がある企業は3割弱
厚生労働省は3月 29 日、令和5年度に実施した不妊治療と仕事の両立に関するアンケート調査結果を公表しました。それによると、不妊治療をしている従業員が受けられる支援制度等がある企業の割合は3割弱(26.5 %)にとどまることがわかりました。一方、不妊治療をしたことがある人のうち、3割弱(26.7 %)は不妊治療と仕事の両立ができなかったと回答しました。その結果、仕事を辞めた人は 10.9 %、不妊治療をやめた人は 7.8 %、雇用形態を変えた人は 7.4 %でした。調査は従業員 10 人以上の企業 1,859 社と男女労働者 2,000 人の回答を集計しました。