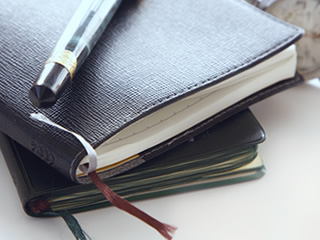<労働基準> ●職種限定労働者の合意なき配転命令は違法 職種限定の労働者に対し、使用者が本人の合意なく実施した他職種への配転命令の可否が争われた訴訟で、最高裁第二小法廷は4月 26 日、労働者の合意のない配転命令は違法だとする初判断を示しました。業務自体が廃止され、配転により労働者の解雇を回避する業務上の必要性を重視した高裁判決を破棄した形です。損害賠償請求の審理をさせるため差し戻しました。最高裁は「労働者と使用者との間に職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は、労働者の個別的同意なしに合意に反する配置転換を命ずる権限を有しない」と指摘しました。労使間の合意を重視する判断を示しました。 ●労働者以外の者の保護措置、事業者に義務化へ 厚生労働省は4月 30 日、危険個所等で事業者が講じる保護措置の対象を労働者以外の者にも拡大する労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を公布しました。令和7年4月から施行します。危険個所への立入禁止等、火気使用禁止、悪天候時の作業禁止、事故発生時の退避など、労働者の安全確保のため事業者に義務づけられている措置の対象範囲を同じ場所にいる労働者以外の者(一人親方、他社の労働者、資材搬入業者、警備員等)にも拡大します。同様に保護具等を使用させる義務がある危険個所等において、事業者が一人親方等に作業を請負わせる場合、その周知を義務づけます。 ●解雇等無効判決後も半数以上が復職せず 厚生労働省が5月 10 日に公表した解雇等無効判決後における復職状況等に関する調査結果によると、半数以上(54.5 %)の者が解雇等無効判決後も復職しなかったことがわかりました。その理由は、復職後の人間関係に懸念(38.9 %)、訴訟で争ううちに退職する気になった(22.2 %)などです。労働者が訴訟を提起した理由も復職は6割強(64.6 %)にとどまり、経済的利益(84.5 %)、公正な解決(80.0 %)、社会的名誉や自尊心(76.2 %)のほうが多い結果となりました。調査は令和5年 10 月~ 11 月、弁護士を対象に直近5年間に終局した解雇・雇止めに係る訴訟事件を聴取しました。231 名から回答を得ました。 <雇用> ●約3割が就活等セクハラを受けた経験ありと回答 厚生労働省は5月 17 日、令和5年度職場のハラスメントに関する実態調査結果を公表しました。その労働者等調査によると、過去3年間に就職活動をした者のうち、就職活動中にセクシュアルハラスメントを受けた経験があると回答した者は約3割に上ることがわかりました。インターンシップ中が 30.1 %、インターンシップ以外の就職活動中が 31.9 %でした。行為者はインターン先で知り合った従業員(47.4 %)、学校の OB・OG訪問を通して知り合った従業員(38.3 %)などが多い結果となりました。調査は 2020 ~ 22 年度卒業で就職活動またはインターンシップをした男女 1,000 名の回答を集計しました。 ●女性活躍に関する情報公表は企業全体に好影響 厚生労働省は5月 17 日、令和5年度女性活躍に関する調査結果を公表し、女性活躍推進法に基づき積極的に情報公表をしている企業ほど、人材確保・定着、職場環境等に好影響を及ぼしている可能性が高いことを示唆しました。調査は、女性活躍に関する積極性として情報公表の項目数に着目し、常用労働者 30 人以上の企業 2,738 社の回答を集計しています。項目数が多い企業ほど、女性管理職比率、女性昇進者比率などが高まる傾向がありますが、加えて企業全体の職場の活性化、残業時間の削減、人材採用の増加、離職者の減少なども概ね項目数が多い企業ほど効果があると回答した割合が多いものとなりました。 ●令和7年1月からオンライン失業認定を全国展開 厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会は5月 20 日、試行的に実施しているオンライン失業認定について、令和7年1月から全国的に拡大する方針を了承しました。これまで9労働局のハローワーク各1ヵ所で障害者、難病、介護、子育て中の者等の来所困難者を対象としてきましたが、来所往復4時間超の者を加えた上で全国展開を図ります。同様に就職支援プログラム対象者へのオンライン失業認定も全国的に拡大します。離島などの市町村取次対象地域を拡大する方針を示しました。 |